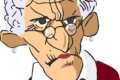知人のTさんは、70代、いくつか持病は持っているものの、毎週水泳クラブに通ったり、庭で野菜を作ったりと、アクティブな生活を送っています。
世の中は、デジタル時代ということで、デジタル化についてゆけないと、これから生きて行けないと言われています。
幸いTさんは、若いころからパソコン大好きの理系人間で、
NEC PC-8801(NEC)FM-7(富士通)が、パーソナルコンピューターとして売り出された1982年ごろから、デジタルに親しんできました。
その後のWindows導入、そしてスマホと移る時代の荒波を仕事を含め乗り越えてきました。
では、Tさんは特別なのでしょうか?
現在毎週通っている水泳クラブのメンバーで見てみましょう。
平均年齢は60歳台半ばで、26人の会員中、全員携帯電話かスマホを持ち、ガラケーで、ネットが見られない人は2名のみです。
水泳のマスターズ大会の予定や結果が常時更新されている会のHP(高齢者が運営)を、多くの会員はよく閲覧しています。
どうする高齢者?デジタル化の壁って本当なの?海外と比べて見よう!
元気な高齢者だから特異な例ということでしょうか?データから現状を詳しく見て行きましょう。
[st-kaiwa1]ネットに強い高齢者もたくさんいるよ! [/st-kaiwa1]どうする高齢者?デジタル化の壁って本当なの?
どうする高齢者?デジタル化の壁って本当なのかを資料から調べてゆきます。
日本における個人のインターネット利用状況(総務省)を高齢者について見ましょう。
ここで、2019年の数値が異常に高くなっていますが、「令和元年調査については調査票の設計が一部例年と異なっていたため、経年比較に際しては注意が必要」と発表されているので、考慮しない方が良いとされます。
これらのデータをもとに、「デジタルの壁」は前回調査では60~64歳あたりにあると考察しましたが、1年後の今回調査では70歳の前あたりに後退したと考えることができる(2022年6月)との考察があります。70歳までは、ほぼ壁(80%以上)を乗り越え、70歳から80歳までの世代が壁を徐々に、後ろに押しやりつつあるという状況ではないでしょうか?
デジタル化で本当に効率アップとなったのか?
2021年9月にデジタル庁が発足してから、めだった成果はあったのでしょうか?
コロナ感染関連
デジタルのメリットどころか、過去の中途半端な市町村独自のシステムの採用で、デジタルデータを利用する問題点が続出し、現場に大混乱をもたらしました。
ワクチンの集団接種の予約で、各地で、数分で、予約が満杯となる自治体が全国各地で見られました。
Tさんの場合も、市の1回目のネット予約は2分、1週間後の2回目は1分で終了。地方新聞に報じられ、担当課に電話して、改善を求めましたが、その後、何も対応はありませんでした。
接触確認アプリCOCOAの事例 感染をいち早く、とらえ、感染ルートを調査したり、通知できると、政府が発表し、Tさんもいち早く導入しましたが、感染情報がトラップできていなかった時期があることが後でわかったり、たびたびのトラブルで、ほとんど役に立つことなく、停止、最近になって役目は終わったと、アプリをアンインストールしてくれとなりました。
韓国など、海外では少なくとも一時期、感染ルートを特定するのに、有効に働いていました。台湾は、マスクの供給も含め最もうまく使った例でしょう。
どれだけの費用をかけてどんな成果があったのか、なかったのか?その原因は?などいまだに、何の検証もないままです。
メリットばかりうたって、結果は知りませんでは、マイナカード、免許証、健康保健証などへの紐づけも同じなの?ということにならないのでしょうか?
また、大阪などで、行われたQRコードによる感染者通知も、その結果が報告されたという記憶がありません。まだやってるのでしょうか?
[st-kaiwa2 r] スマホはできるけど、パソコンは使えない若者もいる! [/st-kaiwa2]
高齢者はどうすれば?
このような状況下で、高齢者は、デジタル化に対してどう取り組めば良いのでしょうか?
デジタル化社会の進行に伴いデジタル・デバイド情報格差が、ますます顕著になりつつあります。
例えば、預金通帳なども、デジタル通帳でなく、新たに口座を開く場合は、従来の通帳だと、毎年手数料を取られるとかということが起こっています。
定期預金にしても、ネット銀行を探せば、年0.2%くらいのところはありますが、街の金融機関の窓口では、0.001%など、ほとんど0に近いのが普通です。
また、申し込みは、ネットからしか受け付けませんというイベントも増えています。
高齢者も覚悟を決めて、政府の例えばマイナポイントなどの施策を利用してやるという気持ちで、立ち向かってゆくしかありません。
同年代でもデジタルに強い人はいますし、教えてもらったり、役所なども不十分とは言え、高齢者のデジタル技術の向上を手助けする講座などあるはずです。
経験から言いますと、デジタルの技術習得は、論理的にというより、トライ&エラーの世界だと思います。習うより慣れろの精神でアプローチするしかありません。
ネットにアクセスできれば、新たな情報を日々受け取り、自分で情報を発信することもできるので、居ながらにして世間とつながることができます。
[st-kaiwa3 r]Gotoイートでは、トリキの錬金術、無限くら寿司次々利用!デジタルデバイド? [/st-kaiwa3]地方の公共交通のシニアパスをLINEで発行し、交通アプリに。青森県弘前市で行われた実証実験では、「高齢者のデジタルの壁」を突破する手段としてLINEが有効で、高齢者の意外な移動実態も把握できました。https://t.co/c5rKlNisWy
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) September 7, 2022
海外の状況
中国の状況
中国の消費者は、WeChat(微信:Line機能にショッピング、支払機能)やMeituan(美団:生活関連サービス企業、電子商取引プラットフォーム)などのアプリを使用すれば、ユーザーは支払い、コミュニケーション、オンラインショッピングなどをモバイルデバイスで簡単に行うことができます。
ベビーブーム世代(1960年代生まれ)では、80%以上がWeChatを1日に複数回利用している。2021年末時点で中国の60歳以上のインターネット利用者は1億1900万人に上り、普及率は43.2%に達している。高齢者のデジタルデバイド(情報格差)が社会問題になっている一方で、1日10時間以上ネットを見ている高齢者は10万人を超えるなどネット中毒が問題になるほどです。
2022年7月末でのアジア主要国でのインターネット普及率(対人口比)を挙げますと、1位の韓国が97.0%、2位台湾94.8%、マレーシア93.8%に続き、日本は93.3%となっています。
人口が多く、農村部も広いためか、中国は69..8%となっています。
シニアが、どの程度か不明ですが、中国では、スマホを持ってないと、コロナ非感染が証明できず、公共機関にも乗れないことや、韓国でのコロナ感染者のスマホを使った追跡システムが稼働していたことを考えると、シニアも、都会ではスマホを使わなくては、外出もできない状態であったと想像されます。
台湾は、マスクがどの薬局にあるかのシステムを初め、感染対策に使って感染抑止に成功した国です。数年前、筆者が台北に行った時も、優先席でタブレットを操作するシニアが当たり前にいました。
今回の新型コロナのパンデミックスで、アジア諸国はシニアを含め、それなりに、スマホなりネットなりを活用したのに、日本は、デジタル化の遅れのさまざまな問題が顕在化したという大きな違いがあったように思えます。
それは単に、日本のシニアの壁のせいだとばかり言い切れません。
高齢者デジタル化の壁へのSNSの反応
[st-kaiwa3] 私たちが苦労してデジタルに習熟せねばならないなら、デジタル庁をつくる政府も、もっと汗をかくべきです。…何がどう便利になるのか。多くの高齢者はほとんど納得していません。国は、国民への説明を怠ってはいませんか。[/st-kaiwa3] 引用:https://twitter.com/US1955/status/1414230920693915652
[st-kaiwa4] 「高齢者」だけだと思わないでほしい。
確かに自分はPCユーザーで、だからこそスマホなんていらない。
新しい技術は宜しいがそれまでの技術を捨てないでくれ。
[/st-kaiwa4] 引用: https://twitter.com/SilvaRegen/status/1413661278829113346
[st-kaiwa5] 「デジタル化には、お金の壁、心の壁、言葉の壁がある。スマホを学びたい意欲ある人には対応方針もあるが、問題はそもそも抵抗感のある人。地道に取り組んでいくしない」
→極論、世代交代を待てか?
[/st-kaiwa5] 引用:https://twitter.com/Albarn0115/status/1403129356738727944
[st-kaiwa6] 最初から「アレもコレも」と色々載せて利権だけ膨らませたから、そもそも利用者のナニがシンプルになるか、じゃなくて「アレもできる、コレもできる、ただしIT必修な、IDとパスワードが、セキュリティが」となって壁高くしちゃったんすよね(・ω・)高齢者ほどデジタル化が恐怖の対象にしかならんし。
[/st-kaiwa6] 引用:https://twitter.com/nami_happy/status/1155150504818688000
まとめ
- 高齢者のデジタル化の壁は、昨年で70歳、現在さらに80歳にまで下がりつつある
- 海外と比べ、日本は、コロナ禍でのデジタル化の利用がうまく行かなかったが、高齢者のせいだとは言えない
- 国や市町村の施策を利用してやるつもりで、個々のシニアが自らデジタル化に取り組まないと得るものが少なく、失うものが大きい
https://umifesta-kyoto.com/elderly-truncated-pension-devaluation-soaring-prices/
https://umifesta-kyoto.com/all-electric-house-regret-soaring-electricity-bill/
https://umifesta-kyoto.com/anticoagulant-rivaroxaban-generic-drug-when-released/
[/st-mybox]