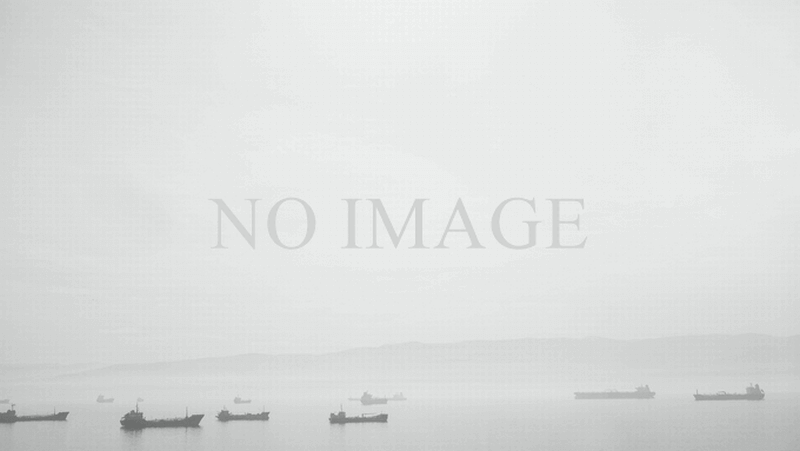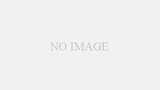夏目漱石の作品にモデルとして登場する寺田寅彦は関東大震災を体験し、後世の災害を予見し、警告した。寺田寅彦とはどんな人物かを知るため主要な著作を角川源義が編集した名著である。
夏目漱石の作品モデルとなった寺田寅彦は科学者であり、エッセイストである。
関東大震災を体験し、後世の災害を予見、警告している。角川書店の創業者角川源義自らが寺田寅彦の作品を編集し、解説している。
寺田寅彦 人生論読本 第十二巻 (角川源義編) 角川書店 1961年(昭和36年)3月10日初版
寺田寅彦のプロフィール
1978年(明治11年)11月28日~1935年(昭和10年)12月31日
物理学者、随筆家、俳人
筆名は吉村冬彦、寅日子、牛頓、藪柑子
東京都麴町区に生まれる。(高知県士族の長男で、軍人の家庭)
11~12才は病弱で、当時の主要な青少年雑誌を読む読書家であった。
1892年(明治25年) 高知県尋常中学に2年生に飛び級で入学をする。
(1894年 日清戦争が起こり、父は予備役で招集される。)
1896年(明治29年) 中学を優等で卒業し、同年熊本第五高等学校に無試験で入学する。
熊本第五高等学校では1~2年は工科で造船を学ぶが、合わず、物理に転科する。
(このころに英語教師夏目漱石、物理学教師田丸拓郎との出会いがあり、科学と文学を目指すきっかけとなる。)
1897年(明治30年) 阪井夏子と学生結婚をする。
1898年(明治31年) 夏目漱石を主宰とした俳句結社紫溟吟社をおこす。
1899年(明治32年) 東京帝国大学理科大学に入学をする。
1900年(明治33年) 東京に妻を呼び西片町に住む。
1903年(明治36年) 東京帝国大理科大学実験物理学科首席で卒業をする。
1904年(明治37年) 東京帝国大理科大学講師となる。
1908年(明治41年) 理学博士号を取得する。
1909年(明治42年) 東京帝国大理科大学助教授に就任をする。
1916年(大正5年) 東京帝国大理科大学教授に就任する。専門は物理学。
父・寺田利正の影響
文久元年(1861年)に土佐藩で井口村刃傷事件は起きた。
上士と郷士との刃傷沙汰で、寺田利正の実の弟に切腹が命じられた。その時の介錯が寺田利正である。
その後、寺田利正は実の弟を介錯したことにより、トラウマとなり、一時期、精神を病む。
郷士への厳しい処罰に郷士たちは怒りが収まらず、その後の土佐勤王党の勢力拡大につながったと言われている。
一方、寺田利正は参加せず、社会を変えるには学問の重要性を考えるようになった。それが寅彦に影響を与えたのではないかとされている。
編者 角川源義のプロフィール
角川源義(かどかわげんよし)
1917年(大正6年)10月9日~1975年(昭和50年)10月27日
実業家、国文学者、俳人、KADOKAWAグループの創業者
富山県中新川郡東水町に三男として生まれる。
父は最初に鮮魚店を営み、のちに米穀店で、成功を収める。
源義は1930年(昭和5年)富山県立神通中学校に入学をする。
国文学と漢文の才能は抜群であるが、数学と英語は苦手で、医師志望熱が薄らいでいった。
父の反対を押し切って国学院大学予科に入学をする。
柳田國男、折口信夫など出会いがある。
1945年(昭和20年)に角川書店を設立した。
場所は東京都板橋区小竹町。
1961年「語り物文芸の発生」で文学博士(國學院大學)。
1972年『雉子の聲』で第20回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞する。
本書の目次
I 寅彦の青春時代
II 寅彦の孤独
III 寅彦火山
寺田寅彦論 辰野隆
寺田寅彦参考文献解題 角川源義
寺田寅彦年譜 角川源義
あとがき 角川源義
本書からの抜粋
(161頁) Ⅲ寅彦火山
関東震災以降
徳川時代に大火のあとごとに幕府から出したいろいろの禁令や心得が、半分でも今の市民の頭に保存されていたら、去年のあの大火はおそらくあれほどにならなかったに相違ない。
江戸の文化は、日本の文化の一つである。ばかにすると罰が当たる。
大正十二年のような地震がいつかは、おそらく数十年ののちには、ふたたび東京を見舞うだろうということは、これを期待する方が、しないよりも、より多く合理的である。その日が来た時に…今度の地震にはなかった集団殺人設備が、いろいろできているだろう。…
(189頁)コーヒー哲学
コーヒーが興奮剤であるとは知っていたが本当にその意味を体験したことはただ一度ある。
病気のために一年以上まったくコーヒーを口にしないでいて、そうしてある秋の日の午後久しぶりで銀座に行ってそのただ一杯を味わった。そうしてぶらぶら歩いて日比谷辺まで来るとなんだかその辺の様子が平時と違うような気がした。公園の木立も行きかう電車もすべての常住的なものがひどく美しく明るく愉快なもののように思われ…
(208頁)
西鶴の恋愛論
…姫は断然その勧告をはねつけて一流の「不義論」を陳述したという話がある。その姫の言葉は「われ命を惜しむにあらねども、身の上に不義はなし。人間として生をうけて、女の男たちただひとり持つこと、これ作法なり。あの者下々を思ふはこれ縁の道なり。…男なき女の一生にひとりの男を、不義とは申されまじ。…昔より試しあり…」というのである。現代ならかなり保守的な女学舎でも言いそうなことであるが、…
(210頁) 科学者にもいろいろな型がある。馬琴型のりっぱな科学者も決してまれではない。
…しかしまた一方では西鶴型のすぐれた科学者もときに出現し、そうしてそういう学者の中におうおう画期的な大発見、破天荒の大理論を遂げる人が生まれるようである。
(222頁) 寺田寅彦論 辰野隆
…「そうか、かれが椎茸を食って前歯を折った水島君、『首くくりの力学』の寒月君なのか」とあらためて、そのやせたあまり人目に立たぬ、むしろいなかの小学校の先生のような小壮物理学者にてのち『三四郎』の中の野々宮宗八君を尊敬の念を込めて見直したのであった。…
まとめ
・漱石の時代に科学者の視点で書かれたエッセーはやはり、一味違う。特に関東大震災の教訓は現代への警鐘であり、科学的に予言した奥深いものがある。
・漱石の作品のモデルとして、しばしば登場する寺田寅彦は、漱石が一目置いている存在である。
・寺田寅彦も偉大であるが、彼の作品をまとめた編者も偉大である。KADOKAWAグループの創業者。