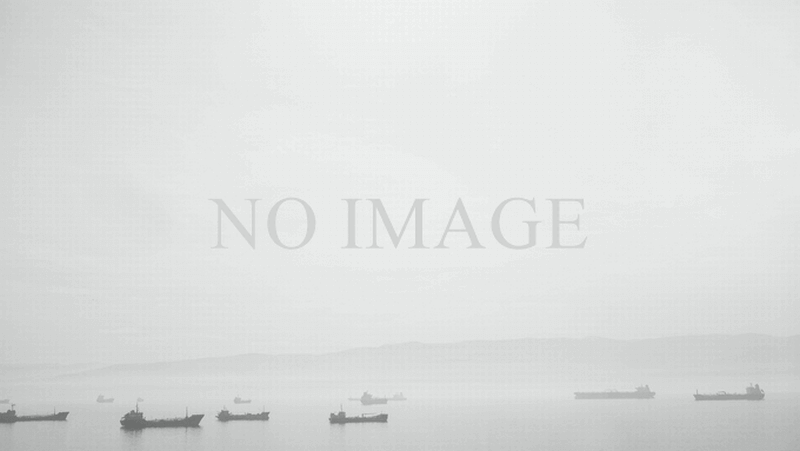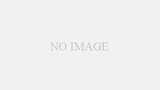2024年にアメリカテレビドラマ“SHOGUN”が世界中の注目を浴びました。16世紀の日本の情景、背景が事細かく正確に描かれています。フロイスの書物が参考になったのか?
第三章「日本覚書」を読む(69頁~)では、ヨーロッパと日本の比較が詳細に記されているために、当時の日本人の習俗、各職業の外見から、仕草、心の内面まで知ることができます。
(例えば)修道院の世俗的財産は、われらにおいては共有である。仏僧らは、みな自分の財産を有し、私腹を肥やすための金儲けに余念がない。…89頁
「フロイスの覚書」 松田穀一、E・ヨリッセン著 中公新書 (中央公論社) 1983年10月25日発行
著者松田穀一のプロフィール
1921年(大正10年)高松市に生まれる。
1944年に上智大学文学部卒業。文学博士
京都外国語大学(大学院)教授。
1981年、訳書(共著)「フロイス 日本史」(全12巻)により、菊池鑑賞、毎日出版文化賞を受ける。
著書…「南蛮資料の発見」、「近代初期日本関係南蛮資料の研究」、「史譚天正遣欧使節」、「黄金のゴア盛衰記」他
著者E・ヨリッセンのプロフィール
Engelbert Jorissen
1956年、西ドイツに生まれる。
ケルン大学文学部卒業。日本文学専攻。
1980年~1983年、ケルン大学専任講師。
京都市立芸術大学講師、
1980年ポルトガルより、カモンイス賞を受ける。
1983年、ケルン大学より学位を受ける。
論文「カモンイスとピント両著の形成と構成」他
本書の目次
第一章 謎を秘めた文章
第二章 十六世紀以前のヨーロッパに伝えられた日本記事
第三章 「日本覚書」を読む
第四章 「ヨーロッパでは…」の補足と検討
第五章 日本とヨーロッパの風習の相違について
本書からの抜粋
(68頁) 11 われらにおいては、顔に刀傷があるのを醜悪とみなす。日本人は、それを誇り、よく治療しないので、いっそう醜さを増す。
男性の衣服について
① われらの衣服は、ほとんど一年の四季を通じて同じである。日本人は一年に三度変える。すなわち夏帷子(ナツカタピラ)、秋袷(アキアワセ)、冬着(フユキモノ)。
(71頁)
⑲われらにおいては、ハンカチーフは非常に薄い布で、刺繍をされたり、糸をほぐした飾りがつけられたりしている。日本人のそれは粗い麻屑(リテイロ)であり、その他のは紙である。
㉗われらは散歩を、おおいに慰安(となり)、健康(によく)気晴らしだと考えている。日本人はそれを全くおこなわず、むしろそれを不思議とし、われらがそれを苦労とか苦行とかのためにするものとみなす。
(82頁) 第Ⅱ章 女性、その風采と衣服について
45 われらにおいては、女性が文字を書く心得はあまり普及していない。日本の貴婦人においては、もしその心得がなければ格が下がるものとされる。
(87頁) 第Ⅲ章 児童、およびその風習に関して
8 われらにおいては俗人の教師について読み書きを学ぶ。日本では、すべての子供が仏僧の寺で学習する。
11 ヨーロッパの子供は、青年になって、口上一つ伝えることができない。日本の子供は十歳でも、それを伝える判断力と賢明さにおいて五十歳にも見える。
12 われらにおいてはニ十歳の男でも、ほとんどまだ剣を帯びない。日本の十二、三歳の少年は刀(カタナ)と脇差(ワキザシ)とを帯びて行く。
(90頁) 第Ⅳ章 仏僧、およびその風習について
12 われらにおいては、いかなる場合も聖職者が君侯や領主の使者となって行くことはない。
日本の殿(トノ)は、仏僧を戦争の使者、また武略として用いる。
(98~100頁)第Ⅵ章 日本人の食事と飲酒の仕方について
1 われらは、すべての物を手で食べる。日本人は、男女とも、幼児の時から二本の棒で食べる。
21 われらは、食事の始めと終わりとに手を洗う。日本人は食物に手をふれないから、手を洗う必要がない。
(115~116頁) 第IX章 病気、医者、および薬について
1われらにおいては、瘰癧(るいれき)、結石、足痛風、およびペスト(といった病)は日常茶飯事である。日本ではこれらすべての病が稀である。
2 われらは、(治療の際に)瀉血をおこなう。日本人は(治療の際に)草を付けた焼きごて(灸)を用いる。
8 ヨーロッパ人の肉体は繊弱なので、健康の恢復はたいそう遅い。日本人の肉体は強健なので、重傷、骨折、潰瘍、および災厄からも(われら)以上の見事さで、常態に復帰するし、それがまたじつに速やかである。
ルイス・フロイスの足跡(年表)
1548 16歳でイエスズ会に入会、インド・ゴアへ
ゴアでフランシスコ・ザビエルに会う
1561 ゴアで司祭に叙階される
1563 31歳九州上陸。布教活動開始
同僚フェルナンデスから日本語、風習学習
1564 京都入り、ガスパル・ヴィレラに会う
1565 三好党に追われ堺へ
1566 京都地区の布教責任者となる
1569 二条御所建築現場で織田信長と対面
機内の布教活動を許可される
1580 来日したアレッサ・ヴァリニャーノの通訳、
同行して、安土城で信長に謁見
1582 (織田信長・本能寺の変)
1583 布教を離れて日本活動記録作成に専念
1587 (豊臣秀吉・伴天連追放令)
長崎へ
1590 ヴァリニャーノ遣欧使節団の秀吉謁見同行
1592 ヴァリニャーノとマカオに行く
1595 長崎に戻る
1597 26人カトリック信者が処刑される。(長崎)
1597 65歳没する
コメント
(読書メーター)
男性・女性・児童・宗教・病気・書物・家屋・船・演劇などについて、ヨーロッパと日本の違いを箇条書きで、いくつもいくつも書かれていて、とても面白い。スルドイところもあれば、偏見に満ちたところもある。 図書館本 ななめ読み
昔の日本とヨーロッパ(一部)の習慣の違いが面白い😆当時の日本で、そんなに頻繁に(身近に)人が殺されていたの?😒今の日本では考えられ無い所もあるけど、納得するところも多々あり。
さすが宣教目的だけあって、なにげに仏僧をボロクソ叩いてゐる點が、逆に微笑ましいとともに滑稽に感じた。そりゃ立場上、肯定できないわなあ。
(BOOK OFF レビュー)
細かい性格だったらしいルイス・フロイスの覚書メモ。 ”ヨーロッパでは・・・、日本では・・・・”と文化・風習の違いを細かに箇条書きにしている。日本に来る宣教師達の為に書かれたメモらしい。ヨーロッパから見た日本の不思議なところ、そしてその時代の日本の風習が分かる楽しい本。 ただし.フロイスはポルトガルの田舎者だから”ヨーロッパでは・・・”の文章も本当にヨーロッパの行われていたことかは妖しいらしい。
16世紀の戦国時代の真っただ中に、…、ポルトガルと日本の文化比較にスポットを当てた本。… 特に面白かったのをいくつかあげると、 ・ヨーロッパでは夫婦が財産を共有するが、日本では夫と妻別々に財産を持つ。 ・ヨーロッパでは女性が葡萄酒を飲むのを非礼とされるが、日本では女性の飲酒が頻繁であり、時には酩酊するまで飲む。 ・我々は他人から強要されることなく酒を飲むが、日本では無理に勧めあうので、ある者は前後不覚になる。 当時から日本は、食事の時に箸をつかっていましたが、ヨーロッパは…
まとめ
・16世紀の日本人の庶民から武士までの生活習慣や心の内面まで事細かくわかるように描かれています。当時を知るのに最上級の文献である。
・ヨーロッパと比較しているために、例えばヨーロッパではまだ、食事にナイフ、フォークは広まってはおらず、手で食べているのがわかります。(フォークはカトリーヌ・ド・メディチ王妃がフランスにもたらしたが、広まるには時間がかかった。)
・2024年の米国テレビドラマ“SHOGUN”の日本の時代考証が正確なのは、もしかして、この本を参考にした?