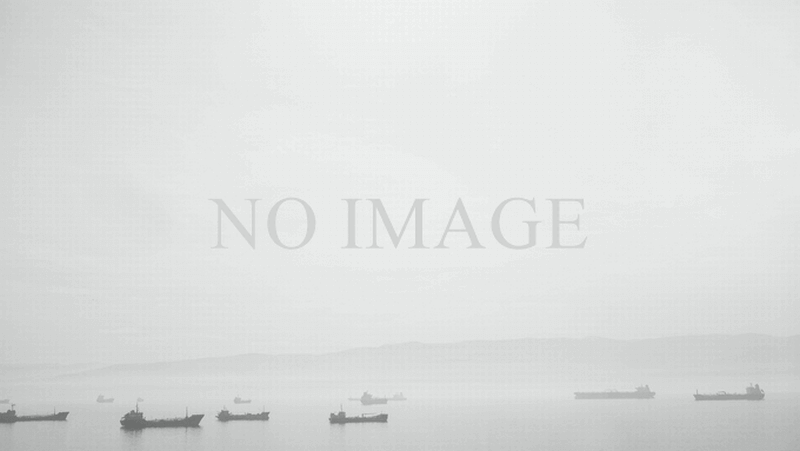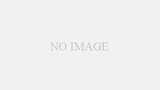本書は内容盛りだくさんで、飽きさせない。
北里柴三郎が苦心して、立ち上げた伝染病研究所は国の傘下に入り、利益・実績をあげて順風満帆であったが、いきなり、国に乗っ取られて、北里柴三郎は放り出される。この時代にもあったのだ。まだこの時代は報道忖度がなかったので、その酷さは衆目の知るところであぅた。
しかし、防げなかった。もっとも、凄いのは生前の福沢諭吉が心配し、予見し、その時のための指示をすでに出していたことだ。詳しくは本編を読んでください。
ほかに、志賀潔や、野口英世についても詳しい記述がある。
上山明博著『北里柴三郎(副題 感染症と闘いつづけた男)』 青土社 2021年9月30日 初版
北里柴三郎氏のプロフィール
(本書329頁より抜粋)
北里柴三郎
嘉永5年12月20日(1853年1月29日)~昭和6年6月13日(1931年)
・北里柴三郎は熊本県の人
・明治十六年東京大学医学部を卒業、十八年ドイツに留学しコッホ博士に師事して細菌学を修め、破傷風菌の純粋培養に成功して、世界の医学会を驚かせた。
・留学期限の切れた後は特に宮内省よりの御下賜金で研究を続け世界学会から認められた。
・明治二十四年医学博士の学位を受け、二十五年帰朝して血清療法の研究を続け、
・明治二十九年内務省伝染研究所所長となり、
・大正五年同研究所が内務省から文部省に移管されるとき反対して部下の北島秦、宮島格博士などと共に職を去って北里研究所をおこし、官学に対峙し一時北研の名声は官立伝研を凌駕した。
・大正八年東京医師会が成立するやその会長に押され日本医界の一大勢力となった。
・また大正九年慶応大学医学部の創立と共に部長となり所謂北里系の諸学者を教授とし、官学に対抗する勢力を築いた。
☆ 第一回ノーベル生理学・医学賞の候補に上がる。
☆ 1909年ドイツ:星章附赤鷲第二等勲章、1910年ノルウェー:聖オーラヴ第二等甲級勲章、1914年フランス;レジオンドヌール勲章コマンドゥール
☆ 2024年7月3日発行の千円の新紙幣に肖像画として使われている。
著作者 上山明博氏のプロフィール
上山明博
1955年10月8日~
・岐阜県生まれ・東京在住
・ノンフィクション作家、記録文学作家
・著作は
『「うま味」を発見した男』 2011年
『関東大震災を予知した二人の男』 2013年
『地震学を作った男・大森房吉』2018年
本書の目次
プロローグ
第一章 ペスト菌発見
第二章 医道論と衛生学
第三章 コッホの下で
第四章 伝染病研究所
第五章 文部省移管事件
第六章 衣鉢を継ぐ人
第七章 隠れた功績
エピローグ
本書からの抜粋
(20頁) …世界を席巻した微生物学は、目まぐるしい勢いで進展を続けた。ロベルト・コッホによって「微生物学(Mikrobiologie)マイクロバイオロジー」が創始され、「微生物の狩人(Miklobe Hunter)マイクロ・ハンターの時代」が開幕した。爾来、一八七三年のらい菌の発見、一八七六年の炭そ菌の発見、一八八〇年の腸チフス菌の発見、一八八二年の結核菌の発見、一八八三年のジフテリア菌の発見、一八八四年のコレラ菌の発見、一八八四年の破傷風菌の発見、一八八五年の大腸菌の発見、一八八六年の肺球菌の発見など…。
(82頁) …今から医学に入るものは、大いに奮発勉励し、この悪弊を捨て、医道の真意を理解せねばならない。 今の学生の風潮をよく見ると、その意志は薄弱で贅沢に走り、うわべを飾るだけで満足している。医学生の全部が金持ちの子ではなく、東大生もその半数は人民の血税を学資としている。人民は日夜辛苦して一日も休む暇なく困窮の中で納税した金なのに、それを無駄遣いして知らぬ顔をし、自分の実力で学問が進歩するのだから、国が資金を与えるのと思い違いをしているのなら、とんでもないことである。このようなものが就職すると栄華を求め、更には病気を未然に防ぐより増えるのを欲するようになれば、人民や国に対しても面白くない。自分に賛同の有志は一緒に憤怒し、この悪弊を今や洗い去ろうではないか。明治十一年四月某日北里柴三郎述(「医道論」北里柴三郎、私家版、明治十一年)
(128頁~132,133頁) 爾来、破傷風菌の純粋培養はできないとする考えが、当時の医学会の定説となった。…北里から破傷風菌の純粋培養に成功したという報告を受けたコッホは、すぐには信じられなかった。コッホが信じなかったのは北里が培養実験を始めてからまだ二カ月しか経っていなかったからだ。…極めて短い期間に成し遂げたことに、コッホは素直に驚き、北里を称賛した。
(142頁) 北里とベーリングの二人の研究を指導し、常に間近で見守ってきたコッホが証言する通り、世界初の血清法は北里によって創案され、破傷風の研究によって成し遂げられた。第一回ノーベル賞生理学・医学賞は、破傷風の研究によって血清療法を創出した北里柴三郎が授賞すべきであることは明らかである。
コメント
(アマゾンレビュー)
信頼が置ける詳細な北里柴三郎の伝記は案外少ないです。
こちらの本は巻末に大量の参考文献が明記されており信頼が置けます。
1890年の破傷風菌の血清療法の論文と照らし合わしながら読みましたが
おかしそうなところはありませんでした。
(楽天レビュー)
北里博士の生き方に触れて
自分はK県の国立大学の医学部出身なので、北里博士の生家のある小国町にも行った事があります。 帝国大学出身でありながら、帝国大学の権威主義を嫌って患者さん主体の医療に一生をかけた博士の生き方に強く賛同しました。
まとめ
・北里柴三郎は生涯一貫して、私利私欲なく、研究への情熱は誰よりも強烈であった。
・北里柴三郎は多くの研究者を育て上げた(志賀潔、秦佐八郎。野口英世など)。
・慶應義塾医学部創設にあたって、本人は無給で全面協力し、優秀な門下生を惜しみなく教授として、送り出した。