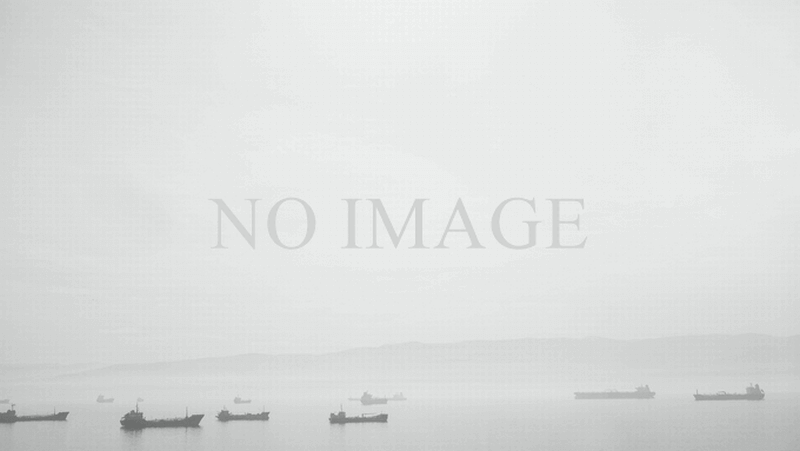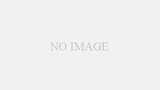鎖国から、解放された明治初期、生真面目な武家の子息は眩いまでの西欧文明に翻弄されながらも確実に吸収し、改めて日本を見つめなおす。寺島実郎氏の力作である。「ニ十世紀と格闘した先人たち」を紹介する。
「ニ十世紀と格闘した先人たち」を著した経済学者の寺島実郎氏は、時々地上波に登場している。いつも的確なコメントをしています。政府の政策に辛口もあり、信頼に足る評論家である。
「ニ十世紀と格闘した先人たち」(副題 一九〇〇年 アジア・アメリカの興隆) 平成27年9月1日 寺島実郎 新潮文庫
寺島実郎氏 のプロフィール
・1947年(昭和22年)に生まれる。
・北海道出身。
・1973年早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。
・1973年三井物産入社。
・ワシントン事務所長。三井物産戦略研究所長。三井物産常務執行役員を務めた。
・他に(財)日本総合研究所理事長。多摩大学学長。三井物産戦略研究所会長。
・著作物として『新経済主義宣言』(石橋湛山賞受賞)、『ワシントン戦略読本』、『能力のレッスン正気の時代のために』、『世界を知る力』、『リベラル再生の基軸 能力のレッスンⅣ』など。
本書の目次
はじめに
第一章 アメリカの世紀がアジア太平洋にもたらしたもの
第二章 国際社会と格闘した日本人
第三章 アジアの自尊を追い求めた男たち
第四章 二十世紀再考―付言しておくべきことと総括
終わりに
解説 藤原帰一
本書からの抜粋
(21頁) なんといっても、秋山真之の米国留学の圧巻は、一八九八年に米西戦争がはじまると、観戦武官として実戦を観察する機会を得たことである。六月九日にフロリダのタンパ港で海軍の運送船「セグランサ号」(四千三十三トン)に乗り込み、約二か月間にわたり米海軍の戦いを現場で目撃したのである。一万六千人の兵士が上陸したサンチャゴ湾揚陸作戦、さらにはサンチャゴ港閉塞作戦。さらには七月三日の海戦を観察している。
(78頁) 袖井林次郎の『拝啓マッカーサー元帥様―占領下の日本人の手紙』(大月書店、一九八五年)であろう。この本は占領下の日本人がマッカーサー元帥宛に送った五十万通にものぼる手紙のうちマッカーサー記念館などに保存されたものなどを解析したものであり、敗戦という極限状況の下での日本人心理が浮き彫りにされている、心に残るのは日本人の卑屈さであり、昨日まで「鬼畜米英」と言っていた人間が、マッカーサーを父や神として称え、「米国の属国となし下され」とすり寄る変わり身の早さである。時代の空気を察知して「長いものに巻かれろ」「バスに乗り遅れるな」という日本人の軽薄なまでの変容性は、今日まで続く性向であり、寒々とした気持ちにさせられる。
(131頁) 大拙は、「敗戦」を「終戦」と言い換える日本人の欺瞞を指摘し、日本は終戦ではなく無条件降伏したことを直視すべきとする。そして,降伏は恥辱でも不名誉でもなく、力もないのに抗戦を続けることこそ非合理的であるという。「一億玉砕」とか「臣道実践」などといって合理的理知を失ってきた日本人の傾向を省察し、合理主義・人格的倫理観・自主的思索力・師子王的独立独行性の大切さを主張するのである。
(304頁) 戦後、日中間に国交が無かった時代に、石橋湛山は一九五九年と一九六三年の二度、周恩来の招請で訪中を果たした。一九五七年に体調を崩し、わずか二カ月で首相を辞任した石橋だったが、「日中国交回復と友好関係の確立」をライフワークと考え、行動を続けていた。彼は、一九五一年以降の日米安保体制を否定するものではなかったが、大陸の「共産中国」との関係改善は、日米親善を阻害するものではないことを、繰り返し主張していた。
コメント
(アマゾンレビュー)
限られた数の日本人だが、当時のエリート達の共通した海外を意識した国家意識の危機感というものが日本を形作ってきた事が分かる。しかし、今の日本には社会的エリートたるべき人々が見えない。
さすがに元商社マン、物産マンだ。こういう本こそ、今の若者の必読書と思う。
団塊の世代の一人として、寺島ファンとして、目から鱗でした。
日本の歴史教育において最も欠けているのは20世紀の日本に関わること。こういう本の出版を契機として、近世日本の勉強が進められることを期待したいものと思いました。
(「読書メーター」のコメント)
個人の生き様を通じて、二十世紀の流れが見えるので面白い。そして、これらがたった百年前の出来事であることを想い、改めて驚かされる。本著で描かれた世界史のうねりは決して遠い昔話ではなく、今日の世界も未だ、その只中にあるのだろう。
筆者の感想
マッカーサーの項目で、『心に残るのは日本人の卑屈さであり、昨日まで「鬼畜米英」と言っていた人間が』とある。敗戦後すぐの日本人男性の浅ましさがうかがえる。それまで、特高警察や、陸軍は極端に威張って、日本国民を見下していたが、敗戦後、アメリカ兵にへつらう変わり身の早さ、日本人男性の姿は、当時の日本女性(大和なでしこ)には情けなく映る。
皆がそうではない。気骨のある日本人男性もいたのである。死線を超えた復員兵たちは内地に戻って、日本人いじめをしているヤクザたちに一人で立ち向かっている。また、戦後は、寝る間も惜しまず、必死で復興に尽力して働いた。その結果、のちの日本バブルとなって、花開く。敗戦してしまって、子供たちに惨めな未来を残すわけにはできないと必死であった。(現代の大人たちは子供たちの未来を豊かなものにする努力をしているか。)
まとめ
・鎖国から解放された明治時代。生真面目な武家の子息は欧米のまばゆい文化に翻弄され
ながらも確実に吸収していく姿が描かれています。
・明治は国内に変革をもたらしただけではなく、新興国の日本に対する欧米の興味がブームを引き起こしています。
・この本の前半は明治を起点として活躍した日本人、日本に接点のある外国人をテーマに描かれている。最後の第四章は歴史の流れの現在の日本の立ち位置。またこれからの歩むべき道が示唆されています。