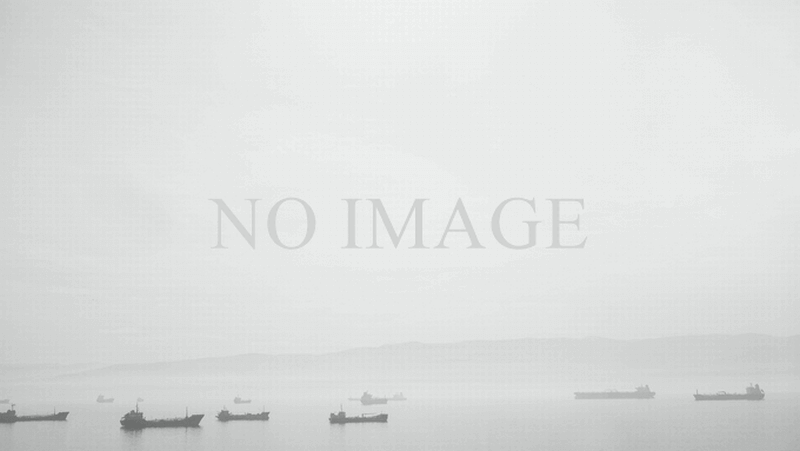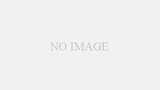大抵の人は宇宙の起源や宇宙の歴史、宇宙の果てを知らない。空を見上げれば、身近にあるのだが。この本は前知識のない我々のような門外漢にでも、出来るだけ分かりやすく解説を試みた秀作である。
書名「ホーキング、宇宙を語るービッグバンからブラックホールまで」
早川書房 1989年6月15日初版
著者プロフィール
S・W・ホーキング( Stephen William Hawking)
1942年、オックスフォードに生まれる。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学で物理学と宇宙論を専攻。早くから理論物理学の第一人者として認められ、1974年史上最年少の32歳でイギリス王立協会会員となる。ケンブリッジ大学ルーカス記念講座教授。
翻訳者プロフィール
林 一(はやし はじめ)
1933年、台北市に生まれる。立教大学理学部卒業。昭和薬科大学名誉教授。専攻は物理学、科学史。著書に、『やさしい相対論』(東京図書)、『薬学のためのアリバイ工作』(海鳴社)など、訳書に、『ゲーテル、エッシャー、バッハ』(白揚社、共訳)などがある。
本書の目次
謝辞―まえがきにかえて
序
1 私たちの宇宙像
2 空間と時間
3 膨張する宇宙
4 不確定性原理
5 素粒子と自然界の力
6 ブラックホール
7 ブラックホールはそれほど黒くない
8 宇宙の起源と運命
9 時間の矢
10 物理学の統合
11 結論―人間の理性の勝利
アルベルト・アインシュタイン
ガリレオ・ガリレイ
アイザック・ニュートン
用語解説
訳者あとがき
本書からの抜粋
(7~8頁)とはいえ、宇宙の運命と起源に関する基本的観念を、科学教育を受けたことのない人達にも理解できるような形で述べることは可能だ。私は本書でそれを試みたが、私のもくろみが成功したかどうか、これは読者に判断していただくべきことだ。この本に数式を一つ入れるたびに、売れ行きは半減すると教えてくれた人がいる。そこで、数式は一切入れないことに決心した。しかし、とうとう一つだけ入れてしまうことになった。アインシュタインの有名な式E=mc²である。
(25頁)しかし一九二九年にエドウィン・ハップルが、どちらの方角を見ても遠方の銀河は我々から急速に遠ざかっているという画期的な観測を行った。いいかえれば宇宙は膨張しつつあるのだ。これは、天体がびっしり集まっていたことを意味する。
(33~34頁)ガリレオの測定はどの物体もその重さにかかわらず、同じ割合で速さを増していくことを示した。たとえば、一〇メートル進むごとに一メートルの割合で下るような斜面に沿って球を転ばせば、球は一秒後にはほぼ毎秒一メートルの速さ、二秒後には二メートルの速さといった具合に速さを増しながら斜面を落ちていき、その速さは重さがいくらかということはかかわりがない。
(229頁)ガリレオは、惑星が太陽の周りを回っているというコペルニクス説をはやくから信じていたが、公然と支持しはじめたのは、この考えを
支持するために必要な証拠を見いだしてからである。
コメント
(アマゾンレビュー)
難解で哲学書のような本書だが、ホーキング博士のアタマの中を垣間見ることの出来る貴重なエッセイ。読んでよかった
(紀伊国屋レビュー)
一般相対性理論と量子論を基に宇宙の起源について思考を巡らせた本。読んでいて感じたのは、何よりも洗練されたその人となりと語りの上手さ。読み易さを考慮して数式を用いない(E=mc²のみ使用)という制限を付けているが、簡略せずに核心を端的に話しており、内容に深みがある上に頭に入り易かった。そのため知的好奇心を何度もくすぐられた。時間と空間の円錐の概念、膨張する宇宙、ブラックホールの放射などの解説を経て、重力の量子論による宇宙の初期と末期の考察が為される。その内容を含め著者の俯瞰性と探求心にも感服の一冊だった。
(読書メーターコメント)
やっぱり宇宙は素敵だな。辛い時、癒してくれる。人生楽しもうってなるな。
「時間の矢」のところは最高に興奮した。
初学者向けっぽい見た目ながら、相対性理論や量子論について聞きかじった程度の知識では全然ついていけないくらい難しかった。雰囲気で分かったつもりになる分には面白い内容。弱い人間原理という形而上の理論がマジメに科学論として取り上げられてるのがSFちっくで惹かれる。
まとめ
・宇宙に対して深い造詣が無くても、理解できるように工夫された名著である。
・この本を読めば、宇宙に対する我々の立ち位置が漠然と見えてくる。
・宇宙の起源が、また、宇宙が膨張していく様が映像となって頭に浮かび上がる。